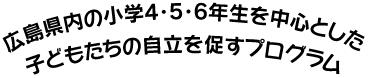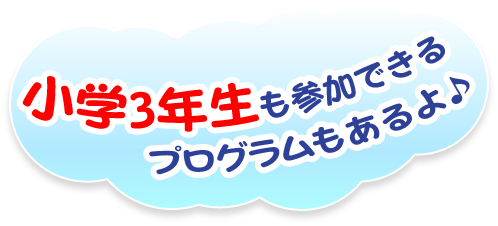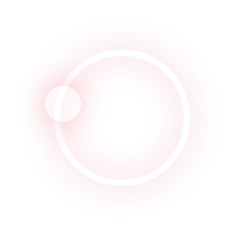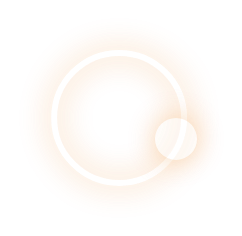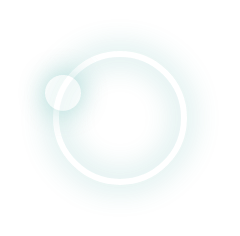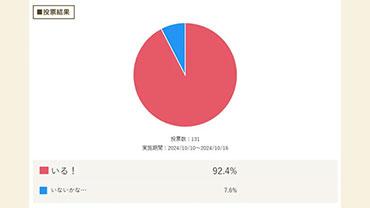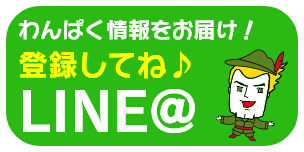2026年1月26日(月)
なぜ高学年になると「自分で考える問題」が増えるの?
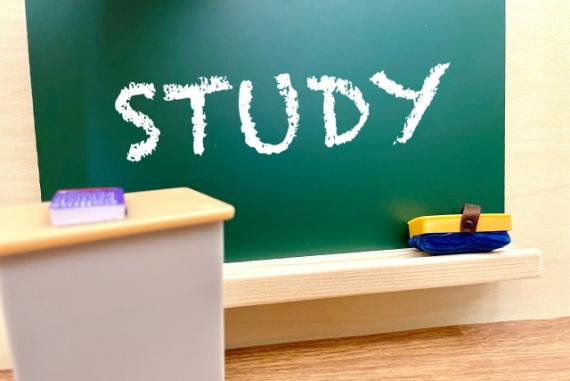
保護者の方の中には、小学校高学年になってからテストや授業で“考える問題”が増えたと感じている人も多いのではないでしょうか。最近のテストは、正確な答えを書くだけではない場合があります。これはただの難化ではなく、学校教育全体の考え方と、次のステップにつながる力を育てる仕組みが背景にあります。その変化の理由を、教育の制度面から見てみましょう。

教育のゴールが「知っている」から「使える」へ変わった

現在の学校教育は、文部科学省が定める「学習指導要領」をもとに行われています。この中で、近年とくに強調されているのが、知識や技能を“覚える”だけでなく、それを“使える力”として身につけることです。
社会の変化が激しく、正解が一つとは限らない時代において、情報を読み取り、自分なりに考え、理由を説明するなどの力が必要になると考えられています。高学年で「考える問題」が増えるのは、この教育の方向転換を、子どもが無理なく体験できる段階として位置づけられているからです。

高学年は「思考力」を本格的に育てる時期

低・中学年では、まず基礎となる知識や技能を身につけます。一方、高学年では、その知識をどう使うかが問われ始めます。
たとえば算数では、「計算が合っているか」だけでなく、「どんな考え方で解いたか」。国語では、「答えが合っているか」よりも、「文をどう読み取ったか」「その理由をどう説明したか」などが重視されます。これは、中学校の学びにも深く直結しています。高学年は、小学校教育のまとめであると同時に、「中学校の学び方」に慣れていく準備期間でもあるのです。

テストの点が下がった=力が落ちたことにはならない?!

子どもがテストで低い点をとってきた場合、焦る保護者は少なくありません。しかし、点数が低いからといって、必ずしも学力が低下しているとは限らない場合があります。考え方や説明を書く問題では、「書き方が足りない」「説明が途中で終わっている」といった理由で減点されることがあります。これは、考えていないからではなく、考えを言葉や式で表しきれていないケースが少なくないということです。
学校がこうした問題を出すのは、正解かどうかだけを見るためではありません。「どこまで理解できているか」「どの段階で考えが止まっているか」を知り、次の指導につなげるためです。そのため、間違いも単なる失敗ではなく、思考の途中経過を示す大切な手がかりとして扱われます。ノートの書き方や途中までの式などが重視されるのは、結果よりも考えの道筋を見ているからです。
点数だけを見ると不安になることもありますが、評価の視点自体が以前よりも細かく、多面的になっている。それが、今の高学年の学びの特徴です。

保護者ができる「評価との向き合い方」

家庭ではつい、子どものテスト結果に対して「なんでここ間違えたの?」「前より点が下がったね」と言ってしまいがちです。しかし昨今の学びでは、答えを出す速さや正解かどうか以上に、考えた過程が重要視されています。
おすすめなのは、「どう考えたの?」「ここまで分かってるんだね」と、子どもの思考を具体的な言葉にさせる声かけです。考えを整理する時間を一緒につくること、点数や正解にこだわらず、子どもが考えた跡が残っているかを追うこと。そして、その先にある、子ども自身の自発性の育成や知的好奇心の向上-そこに目を向けながら、子どもの成長を見守っていきましょう。

出展
文部科学省『学習指導要領「生きる力」』
文部科学省『平成29・30・31年改訂学習指導要領(本文、解説)』
2025年12月17日(水)
冬休みを有意義に!高学年親子の「時間管理」で自立心を育てる

冬休みは、勉強・遊び・ゲーム…やりたいことが一気に増え、生活リズムが乱れやすい時期。特に高学年になると、親が管理しすぎても反発が強まり、かといって放任すると生活サイクルが大きく崩れがちです。そこでおすすめなのが、「時間管理を親子の共同プロジェクト」にする方法。ゲーム感覚で取り組める仕組みを取り入れることで、子どもが自分で考えて予定を組む力を自然と身につけられます。

まずは「やりたいこと」「やるべきこと」を一緒に棚卸し
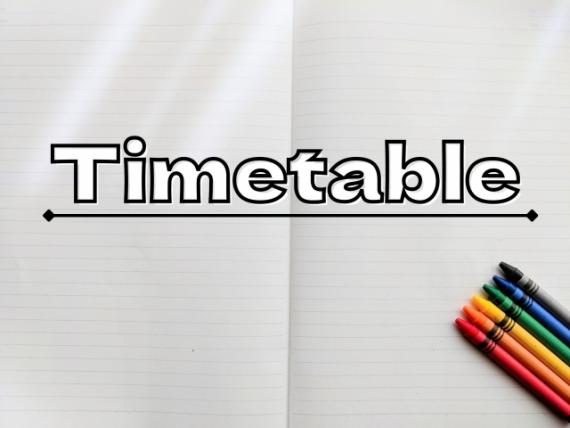
親が一方的に決めるより、最初に親子で「冬休みにやりたいこと」を出し合うのがポイントです。
・「宿題を計画的に終わらせたい」
・「友だちと遊びたい」
・「ゲームの時間もほしい」
・「料理を手伝ってみたい」
・「冬休み中に1冊本を読みたい」
学校の宿題や家庭で決めてほしい習慣に加え、子ども自身の希望をしっかり入れることで、スケジュール作りへの参加意欲が高まります。親子で計画を可視化する共同作業は、その第一歩になります。

スケジュール表をゲーム化して続けやすくする

時間を区切って「勉強」「遊び」と決めるだけだと、子どもは管理されている感覚が強くなりがち。そこで、ポイント制を取り入れたゲーム化スケジュールが効果的です。
例えば、冬休み中の行動をいくつかのカテゴリーに分けて、クリアするとポイントが入る仕組みにします。
●勉強・宿題:国語、算数、漢字練習など → 1ポイント
●読書・学び:好きな本や新聞、図鑑 → 1ポイント
●運動・外遊び:散歩、縄跳び、公園遊び → 0.5〜1ポイント
●手伝い:料理の手伝い、掃除、洗濯たたみ → 0.5ポイント
●自由時間:ゲーム・動画など → 0ポイント(時間設定のみ)
「1日に3ポイント貯めたらOK」「1週間で20ポイント達成したらご褒美」など、親子で目標を決めます。
ポイントがあると、やらされる感が自分で選ぶ、またはクリアすることへ意識が変わり、達成感と自主性が育ちやすくなります。

1日の流れは「3つの基軸」でシンプルに整える

高学年になると、細かい管理より「基軸を決めて任せる」ほうがうまくいきます。おすすめは以下の3つです。
① 起きる時間と寝る時間だけは固定する
② ゲームや動画は「1日◯分」の上限だけ決める
③ 宿題・運動・手伝いは、どれか1つは毎日やる
これだけで生活は大きく乱れにくくなります。文部科学省でも、子どもの健康的な生活には「起床・就寝のリズム」「適度な運動」「メディア利用ルール」の重要性が強調されています。細かい時間割を作るより、「習慣の柱」を立てることが継続のコツです。

振り返りタイムで「できた!」を積み重ねる
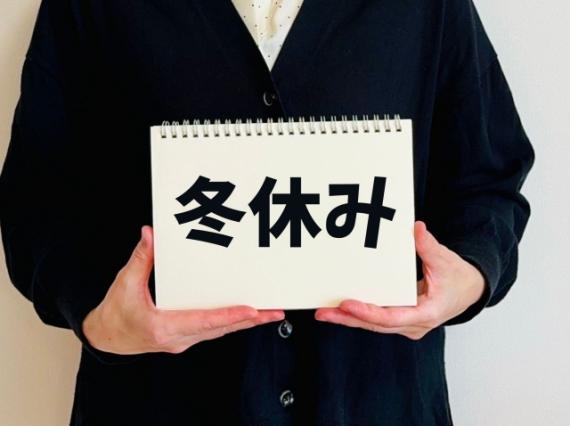
時間管理は、結果より、積み重ねるプロセスが大切。1日の終わりや週末に、短い時間で振り返りを。
・今日のポイント、何ができた?
・明日はどこを変えたい?
・頑張ったことを親子で1つずつ言い合う
この小さな振り返りが、自己肯定感につながります。
また、子どもが決めた計画がうまくいかなかったときも、「叱る」より「調整する」を優先。「どうすれば続けられそう?」と対話することで、自分で考えて修正する力が育ちます。

<出展>
文部科学省「早寝早起き朝ごはん国民運動」
文部科学省「子どもの基本的生活習慣の育成に向けた取組報告書」
子ども家庭庁「健やか親子21と成育基本法」
2025年11月25日(火)
本格的な冬前に見直したい!高学年通学路の安全チェック

朝晩の空気にひんやりとした冷たさを感じるようになると、登下校の景色も少しずつ変わってきます。夕暮れが早まり、通学路は思いのほか暗く、人も車も見えにくくなる季節。
毎日を何気なく歩いている「いつもの道」こそ、冬を前に一度立ち止まって見直してみたいものです。高学年の子どもは行動範囲が広がり、自立も進む時期。だからこそ、“自分で安全を考える力”を育てる絶好のタイミングでもあります。

登下校時刻が変わる冬前の“薄暮時間帯”リスクとは

11月を過ぎると、下校時間の16〜17時台はすでに薄暗くなり、車から子どもの姿が見えにくくなります。実際、交通事故の発生率はこの時間帯に高く、警察庁の統計でも「薄暮時」は年間を通じて注意が呼びかけられています。地域によっては街灯が少ない通学路や、車の抜け道になっている細い道もあります。まずは今の時間帯の明るさを一緒に確かめてみましょう。
「この交差点、夕方は暗くない?」「車、こっちからも来るね」。そんな小さな会話が、子どもの“見る力・考える力”を養います。いつも通る道を、あらためて夕方の目線で歩いてみる。それが安全チェックの第一歩です。

「見える自分」にスイッチを!服装と反射材の力

明るい色の服や反射材(リフレクター)は、命を守る最もシンプルなツールです。データによると、反射材をつけている人は、つけていない人よりも約2倍早く車のライトに照らされて見つけられるといいます。特に高学年の子どもは「ダサい」「友だちにからかわれそう」とためらうこともありますが、「カッコよく光る=かっこいい安全スタイル」と、ポジティブに捉え直すことが大切です。反射材付きのリュックベルトや靴、ヘルメット、キーホルダーなら自然に取り入れられます。
また、夕方の外出時はライトを点ける習慣を。自転車のハンドルライトや腕バンド型のLEDライトなど、「自分が光る」仕組みを味方につけましょう。

下校後や遊び時間帯にも注意。油断が招く交差点トラブル

「学校の行き帰りだけ気をつけていれば大丈夫」。そう思いがちですが、実は事故が起きやすいのは放課後や遊び帰りの時間帯でもあります。政府の調査では、小中学生の交通事故の多くが「登下校中」と「15〜17時台」に集中しています。特に高学年になると、自転車を使う機会が増え、歩行者から自転車利用者へとリスクの形も変わります。
交差点では「横断歩道の前で止まる」「左右を確認してから進む」「手を挙げて渡る」など、基本動作を改めて確認しましょう。
また、友だちとの帰り道でふざけて走り出すなど、油断が事故を招くこともあります。
「急がず・焦らず・まっすぐ帰る」。親が言葉にして伝え続けることで、日々の行動に定着していきます。

家庭と地域で守る“声かけ”で安全の輪を

安全対策は、家庭だけではなく地域全体で支えるものです。親として、毎朝のひと声ルーティンをはじめてはいかがでしょうか。
「反射材つけた?」「ひも、ぶら下がってない?」「渡る前に止まるんだよ」
短い言葉でも、繰り返されることで子どもの意識は確実に育ちます。
また、冬の服装は暗い色が多くなりがち。視認性の高い明るい色や反射付きのアウターを選ぶと安心です。学校通信や地域の掲示板で「暗い交差点」「見通しの悪い場所」などを共有するのも有効です。行政の通学路点検情報や防犯マップを確認すれば、家庭では気づけなかったリスクも見えてきます。

本格的な冬を前に「親子で歩く日」を設けよう

11月は、季節が変わるだけでなく、日常のリズムも少しずつ変わる月です。子どもが毎日使う通学路を、親子で一緒に歩いてみるなど、それだけで、道の段差や暗がり、車の流れ、子どもの歩き方が見えてきます。
“見えない危険”を“見える安全”に変えるのは、ほんの少しの関心と会話、そして習慣です。本格的に寒くなる前のいまこそ、通学路の安全を家族で見直すチャンス。季節の移り変わりを感じながら、安心して歩ける道を、親子で育てていきましょう。

<出展>
警察庁「薄暮時間帯における交通事故防止」
警察庁「反射材・ライト ~薄暮・夜間はつけた光が命を守る~」
文部科学省「通学路における交通安全の確保に向けた取組状況について」
2025年10月14日(火)
秋ならではの読書タイミングを親子で楽しむヒント
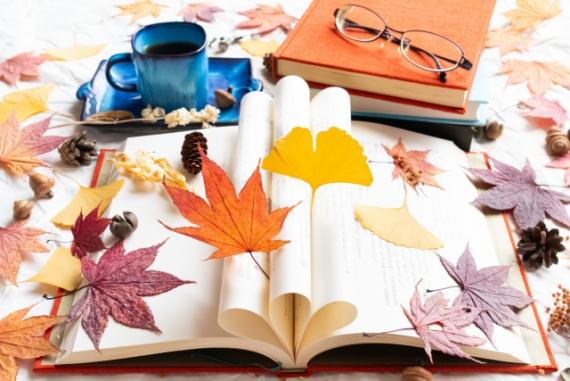
秋の空気がより冷たくなり、家の中で過ごす時間が増えるこの季節。自然と「本を読みたい」と感じる人が増えます。実は、秋という季節は“集中力を高める条件”がいくつも重なる時期でもあります。勉強や読書に向く理由を、科学的・心理的な観点から少しのぞいてみましょう。親子で楽しむ読書時間を、より豊かにするヒントもあわせて紹介します。

秋の夜長がもたらす集中のリズム
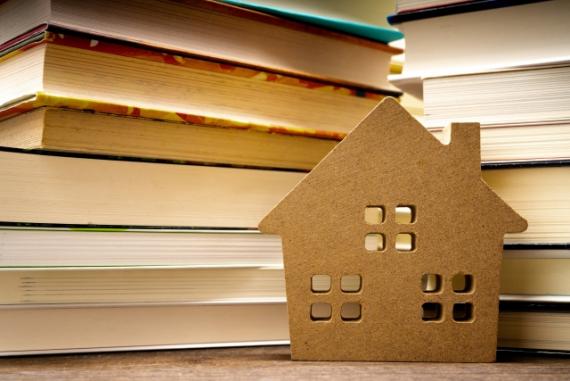
「秋の夜長」という言葉には、単に夜が長いという意味以上の魅力があります。日照時間が短くなり、気温も下がるこの季節、人の体内リズムは静のモードへと切り替わっていきます。夏のように外出やイベントで気持ちが外へ向かうのではなく、落ち着いた時間を過ごしたくなる。これは、メラトニンというホルモンの分泌と関係しています。メラトニンは睡眠の質や体内時計を整える物質で、暗くなる時間が早いほど自然に分泌が促されます。夜のリズムが整うと、心も穏やかに、集中しやすくなるのです。
つまり、秋の環境そのものが「深く集中する夜」をつくってくれます。子どもたちが宿題や読書に向きやすいといわれるのは、理にかなった季節反応ともいえます。

読書が育てる“集中の筋肉”
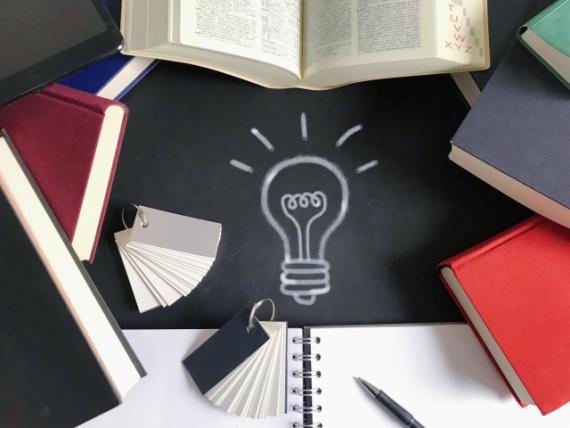
読書の時間は、脳にとってのトレーニングの時間でもあります。文字を追いながら意味を理解し、登場人物の心情を想像し、物語全体の構造をつかむ。この一連の作業は、脳のさまざまな領域を同時に使う複雑な行為です。
読書を重ねることで、集中力の持続時間が自然と伸び、思考を深める力も育ちます。
特に小学校高学年は、抽象的な思考が発達しはじめる時期。物語の裏側を考えたり、登場人物の気持ちを推測したりといった「読解の深み」を楽しめるようになります。
この時期に読書を習慣にしておくことは、将来の学習力や表現力の土台を築くうえで、大きな意味を持ちます。また、読書は「言葉の力を養い、思考や感性を豊かにする基礎的な営み」と位置づけられています。つまり、読書は単なる趣味ではなく、集中力や思考力を育てる「心の筋トレ」なのです。

秋の情景が想像力を刺激する
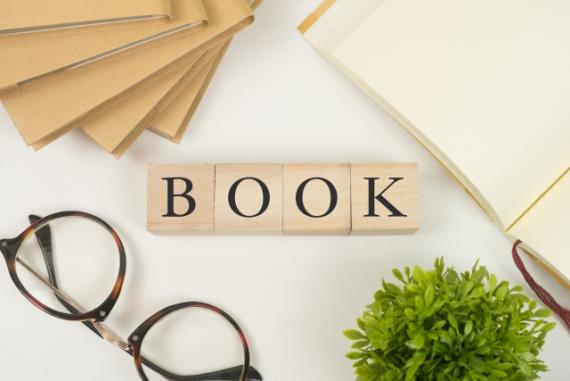
秋が読書に向く理由は、環境リズムだけではありません。
この季節は五感を刺激する素材が豊富。赤や黄に色づく木々、夕暮れの光、冷たい空気、虫の声。こうした自然の変化は、子どもの感性を強く刺激します。例えば、秋を舞台にした物語や、自然をテーマにした詩を読むと、子どもたちは自分の体験と重ね合わせながらイメージをふくらませます。「この景色、見たことあるなぁ」「この匂い、今日の帰り道と同じだなぁ」。そんな共感が、読書体験を生きた感覚として定着させるのです。
読書の内容を親子で語り合うこともおすすめです。「この主人公なら、どんな気持ちだったと思う?」と問いかけたり、「この場面、自分ならどうする?」と話し合うことで、子どもの内面を引き出すきっかけにもなります。
読書は、感性を共有し、親子の心を近づけるコミュニケーションの時間にもなり得ます。

集中を深める読書環境づくり

せっかくの読書の秋。少しの工夫で読書の質を高めることができます。いくつかの例を紹介しましょう。
・照明はやや暖色系に――目に優しく、心を落ち着ける効果があります。
・音の演出を意識――テレビを消し、静かな環境を。虫の声や自然音のBGMも集中を助けます。
・短時間でも決まった時間に読む――「夜9時からの10分読書」など、習慣化がポイントです。
・読後の感想を共有する。――本の内容を口に出して話すことで、記憶が定着しやすくなります。
さらに、読む姿勢を大切にするのもコツです。背筋を伸ばし、足を地面につけて座ると、呼吸が安定し、集中力が持続しやすくなります。ほんの少しの姿勢の違いが、読書の質に大きく影響するのです。
秋は、外の世界がゆっくりと落ち着きを取り戻す季節。静かな時間を持つことが心地よく感じられる今こそ、親子で本に向き合うチャンスです。“集中力を鍛える”というと堅苦しく聞こえますが、読書の時間は本来、心を整え、想像力をひらく豊かな時間。季節の空気を味わいながら、ページをめくるそのひとときが、子どもたちの未来を少しずつ育てていくのかもしれません。

<出展>
文部科学省「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」
文部科学省「第五次『子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画』閣議決定」
文部科学省「子どもたちのために、読書環境の整備を進めましょう」
2025年9月12日(金)
親子で楽しむお月見!秋の夜空に自然と文化を感じる時間を

9月は秋の訪れを感じる季節。夜空に浮かぶ月を見上げると、どこか心が落ち着くような気持ちになります。昔から日本では、満月を愛でる「お月見」の習慣が受け継がれてきました。親子で一緒に月を眺めながら、その背景にある歴史や意味を知ることで、何気ない一晩が特別な時間になるかもしれません。

月を愛でるこころとお月見のはじまり

お月見は、平安時代に中国から伝わった行事が日本独自の風習として定着したものです。旧暦の8月15日にあたる「十五夜」は、もっとも美しい月が見られるとされる夜。稲の収穫を前に、自然の恵みに感謝する意味も込められていました。
現代の暦では、十五夜は毎年日付が変わり、9月中旬から下旬にかけて巡ってきます。9月は空気が澄み、月がくっきりと見えるため、まさにお月見にふさわしい時期といえるでしょう。「ただ月を眺めるだけ」と思うかもしれませんが、月は昔から人々の生活や信仰と深く結びついてきました。時間を計る目安となり、農作業の節目を知らせ、詩や物語を生む源にもなったのです。夜空に浮かぶ月には、先人たちの知恵や祈りが込められているのだと思うと、見上げる気持ちも少し変わってきませんか。

家族でできる小さな工夫でお月見をもっと楽しむ

気候が落ち着く季節だからこそ、ぜひお月見を楽しみたいところ。難しく考えず、テーブルにお団子や秋の果物を並べ、月を見ながら家族でおしゃべりするだけでも立派なお月見になります。
ちょっと工夫するなら、こんな楽しみ方もおすすめです。
・すすきを飾る:すすきは稲穂の代わりとされ、魔除けの意味もあるといわれます。秋の草花と一緒に飾れば、室内でも季節を感じられます。
・月の観察ノート:月の満ち欠けや光の強さを記録してみると、自然へのまなざしが育まれます。
・物語を楽しむ:「竹取物語」や「月のうさぎ」のお話を一緒に読むのも、お月見らしい過ごし方です。
親子で一緒に月を眺めるだけで、「同じものを見ている」という共通体験が生まれます。普段は忙しくてゆっくり話せない夜も、月がよいきっかけになってくれるでしょう。

芋名月と地域ごとのお供え物

十五夜は「芋名月」とも呼ばれ、昔は里芋をお供えする習慣がありました。地域によってはサツマイモや栗、枝豆など、その土地で収穫されたものを供えることも。お月見団子が広まったのは江戸時代といわれていますが、丸い形は満月をかたどり、健やかな成長や幸福を祈る意味が込められています。
このように、お月見の風習は全国一律ではなく、土地の暮らしや自然と深くつながっています。「自分が住む地域ではどうだったかな?」と調べたり、親世代から子へ伝えたりするのも、文化を引き継ぐ大切な時間になりそうです。

秋の夜長に広がるお月見の魅力

9月に入ると、昼間はまだ暑さが残るものの、夜は過ごしやすく、虫の声も心地よく響きます。澄んだ夜空に月を見つけると、ふと日常から解放されるような感覚になることも。
親子でお月見をすることは、単に「月を見る」だけではなく、自然のリズムや文化の奥行きを体感することでもあります。特別な準備をしなくても、ただ夜空を見上げる時間が、子どもにとって忘れられない思い出になるかもしれません。ほんの少し灯りを落として、窓の外に目を向けてみませんか。きっと、静かな月の光が、家族の時間を優しく包んでくれるはずです。

<出展>
農林水産省「季節と餅」
農林水産省 東北農政局「食育ブログ 食(ク)リックひろば」
中国四国農政局 メルマガ「2024.09.10 配信」