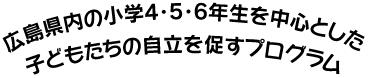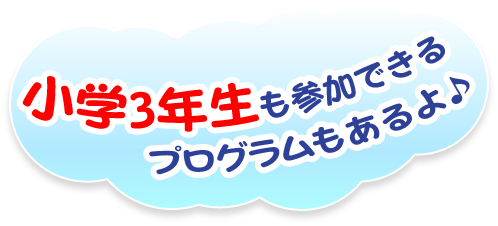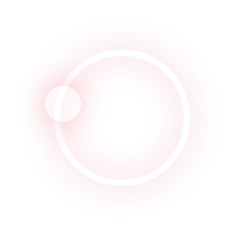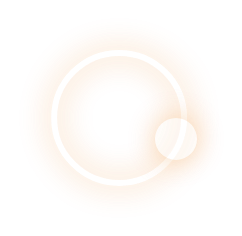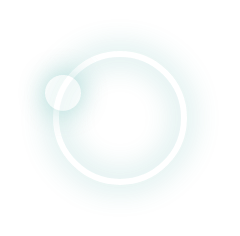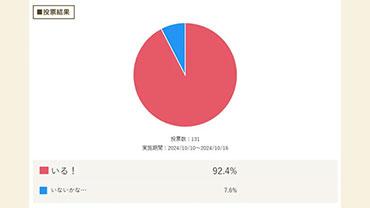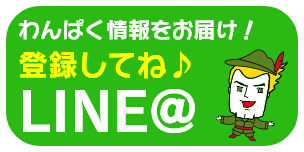2025年11月25日(火)
本格的な冬前に見直したい!高学年通学路の安全チェック

朝晩の空気にひんやりとした冷たさを感じるようになると、登下校の景色も少しずつ変わってきます。夕暮れが早まり、通学路は思いのほか暗く、人も車も見えにくくなる季節。
毎日を何気なく歩いている「いつもの道」こそ、冬を前に一度立ち止まって見直してみたいものです。高学年の子どもは行動範囲が広がり、自立も進む時期。だからこそ、“自分で安全を考える力”を育てる絶好のタイミングでもあります。

登下校時刻が変わる冬前の“薄暮時間帯”リスクとは

11月を過ぎると、下校時間の16〜17時台はすでに薄暗くなり、車から子どもの姿が見えにくくなります。実際、交通事故の発生率はこの時間帯に高く、警察庁の統計でも「薄暮時」は年間を通じて注意が呼びかけられています。地域によっては街灯が少ない通学路や、車の抜け道になっている細い道もあります。まずは今の時間帯の明るさを一緒に確かめてみましょう。
「この交差点、夕方は暗くない?」「車、こっちからも来るね」。そんな小さな会話が、子どもの“見る力・考える力”を養います。いつも通る道を、あらためて夕方の目線で歩いてみる。それが安全チェックの第一歩です。

「見える自分」にスイッチを!服装と反射材の力

明るい色の服や反射材(リフレクター)は、命を守る最もシンプルなツールです。データによると、反射材をつけている人は、つけていない人よりも約2倍早く車のライトに照らされて見つけられるといいます。特に高学年の子どもは「ダサい」「友だちにからかわれそう」とためらうこともありますが、「カッコよく光る=かっこいい安全スタイル」と、ポジティブに捉え直すことが大切です。反射材付きのリュックベルトや靴、ヘルメット、キーホルダーなら自然に取り入れられます。
また、夕方の外出時はライトを点ける習慣を。自転車のハンドルライトや腕バンド型のLEDライトなど、「自分が光る」仕組みを味方につけましょう。

下校後や遊び時間帯にも注意。油断が招く交差点トラブル

「学校の行き帰りだけ気をつけていれば大丈夫」。そう思いがちですが、実は事故が起きやすいのは放課後や遊び帰りの時間帯でもあります。政府の調査では、小中学生の交通事故の多くが「登下校中」と「15〜17時台」に集中しています。特に高学年になると、自転車を使う機会が増え、歩行者から自転車利用者へとリスクの形も変わります。
交差点では「横断歩道の前で止まる」「左右を確認してから進む」「手を挙げて渡る」など、基本動作を改めて確認しましょう。
また、友だちとの帰り道でふざけて走り出すなど、油断が事故を招くこともあります。
「急がず・焦らず・まっすぐ帰る」。親が言葉にして伝え続けることで、日々の行動に定着していきます。

家庭と地域で守る“声かけ”で安全の輪を

安全対策は、家庭だけではなく地域全体で支えるものです。親として、毎朝のひと声ルーティンをはじめてはいかがでしょうか。
「反射材つけた?」「ひも、ぶら下がってない?」「渡る前に止まるんだよ」
短い言葉でも、繰り返されることで子どもの意識は確実に育ちます。
また、冬の服装は暗い色が多くなりがち。視認性の高い明るい色や反射付きのアウターを選ぶと安心です。学校通信や地域の掲示板で「暗い交差点」「見通しの悪い場所」などを共有するのも有効です。行政の通学路点検情報や防犯マップを確認すれば、家庭では気づけなかったリスクも見えてきます。

本格的な冬を前に「親子で歩く日」を設けよう

11月は、季節が変わるだけでなく、日常のリズムも少しずつ変わる月です。子どもが毎日使う通学路を、親子で一緒に歩いてみるなど、それだけで、道の段差や暗がり、車の流れ、子どもの歩き方が見えてきます。
“見えない危険”を“見える安全”に変えるのは、ほんの少しの関心と会話、そして習慣です。本格的に寒くなる前のいまこそ、通学路の安全を家族で見直すチャンス。季節の移り変わりを感じながら、安心して歩ける道を、親子で育てていきましょう。

<出展>
警察庁「薄暮時間帯における交通事故防止」
警察庁「反射材・ライト ~薄暮・夜間はつけた光が命を守る~」
文部科学省「通学路における交通安全の確保に向けた取組状況について」