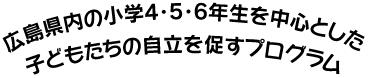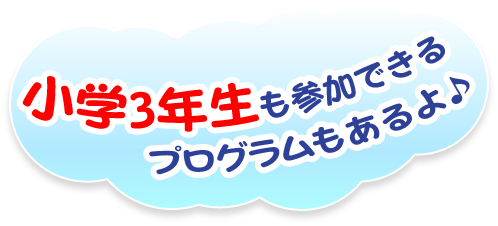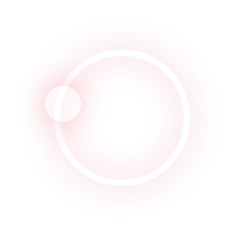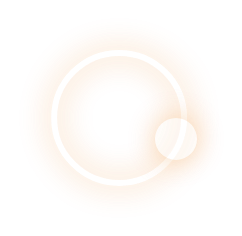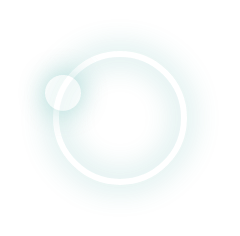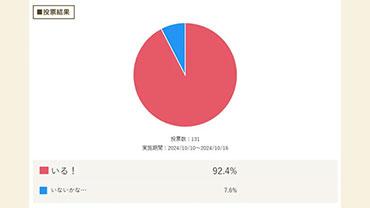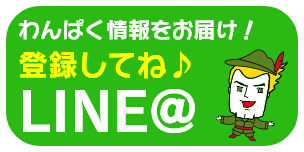2025年10月10日(金)
【よくある相談シリーズ】親子で温泉に行きたいと考えています。気を付けることは?

気温が下がり、温泉が恋しくなる季節になりました。せっかくなら家族みんなで湯に浸かりたい、そう感じる人も多いでしょう。とはいえ「子どもを連れて大丈夫?」「周囲に迷惑をかけないか心配」と不安に思う保護者も少なくありません。親子で安心して温泉を楽しむためのポイントを、フォトグラファー兼温泉ソムリエとして活躍する中野一行さんに聞きました。

安全第一。温泉では“目を離さない”が鉄則

温泉で最も大切なのは安全面です。浴室の床は滑りやすく、転倒や湯船での事故につながることもあります。小学生でも油断せず、常に目を離さないようにしましょう。特に大浴場は、多くの人が利用する公共の場です。「ここはみんなで使う場所」とあらかじめ伝えておくと、子どもも落ち着いて過ごせます。もし湯船で大きな声を出してしまった場合は、一度脱衣所などで気持ちを落ち着かせてから戻るのも良い方法です。体を洗ってから湯に入る、泡を残さない、髪の長い人はまとめるなど、基本のマナーを親が示すことも大切です。

周囲を気にせず過ごせる“貸切湯”や“足湯”もおすすめ

子どもがはしゃいだり、静かにできるか不安な場合は、貸切湯や部屋風呂のある施設を選ぶと安心です。祖父母など複数の大人と一緒に入ると、安全面の確保もしやすくなります。周囲を気にせず、親も子も心から寛げることが何より大事です。また、浅めの子ども用浴槽を備えた施設もあるため、事前にホームページで情報を確認しておくとよいでしょう。比較的値段が高めに設定されている旅館では、子どもの利用を制限している場合もあるため、電話で問い合わせるのが確実です。
そして、足湯を楽しむのもいいでしょう。服を脱ぐ必要がなく、親子で会話を楽しみながら温泉の心地よさを味わえます。「少し熱いね」「気持ちいいね」と交わす何気ないやり取りが、子どもとのいい思い出になります。

子どもにやさしい“ぬるめ”と“単純泉”を選ぼう

温泉の泉質には多様な種類があります。中四国エリアでは稀ですが、酸性泉や硫黄のにおい(硫化水素)が強い温泉は、体に負担を与える可能性があるため、他の選択肢を考えるのが安心です。おすすめは「単純泉(単純温泉)」。成分が薄く、刺激が少ないため、家族でゆったり入浴するのに適しています。単純泉だからといって価値が低いわけではなく、むしろ親子で快適に過ごせる“やさしいお湯”です。「家族の湯」とも呼ばれています。
また、お湯の温度は38〜40度ほどの“ぬるめ”がいいでしょう。のぼせを防ぎ、ゆったり長く楽しめます。入浴前後の水分補給を忘れず、乾燥しやすい季節は保湿ケアも忘れずに。

一緒に入れるのは何歳まで?妊婦さんの入浴は?

男の子は父親、女の子は母親と一緒に入ることが多いですが、逆の場合は年齢制限があることがほとんどです。その年齢は、各自治体によって異なり、条例で定められている場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
一方で、妊婦さんの温泉入浴は「体に無理のない範囲であれば問題ない」と考えられています。日本温泉気候物理医学会による2020年の大規模調査(大分県別府市・鹿児島県指宿市の妊婦1,723名対象)では、温泉入浴が流早産や妊娠高血圧症などの発生に関連しないことが報告されています。熱すぎる湯や急な温度変化を避け、転倒に気をつければ、安心して温泉を楽しむことができます。

温泉は学びの場。文化と社会性を育む時間に

温泉は、親子にとって“学びの場”でもあると考えています。多くの人が利用する公共の空間では、「静かに入る」「譲り合う」「周囲を思いやる」といった社会性を自然に学ぶことができるのです。
また、日本では古くから温泉文化が人々の暮らしとともにありました。『日本書紀』には温泉の記述が登場し、江戸時代には藩主が湯治に訪れています。広島藩の浅野家も、現在の広島市佐伯区・湯の山温泉に湯治場を設けており、建物は今も国の重要有形民俗文化財として残っています。温泉は、何百年も前の人々と同じ体験を共有できる“生きた歴史”。親子で湯に浸かりながら、「昔の人もこの湯で癒やされたんだね」と話す時間は、何より温かい学びのひとときになるでしょう。
安全とマナーを守りながら、親子で過ごす温泉時間を心ゆくまで楽しんでください。


- 中野一行 フリーランスフォトグラファー/温泉ソムリエ
- 宮城県出身、広島市在住。札幌の写真学校で学び、東京のスタジオで修行を積んだのち、広島で経験を重ねて2001年に独立。以降、雑誌や広告、Webなど幅広い分野で撮影を手がけている。飲食店や商業施設の撮影実績は数千件を超える。日本でも数少ない「2つ星 温泉ソムリエ」の資格を持ち、温泉撮影は最も得意。湯けむりの表情や光の揺らぎまで切り取る“温泉撮影のスペシャリスト”として知られる。著書に『中国・四国かけ流し温泉ガイド』。