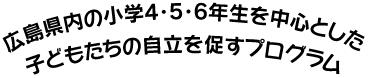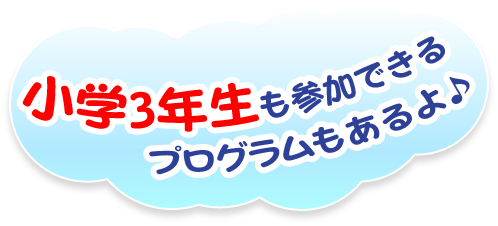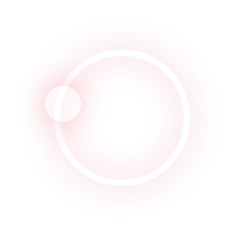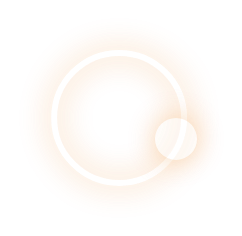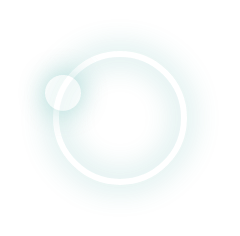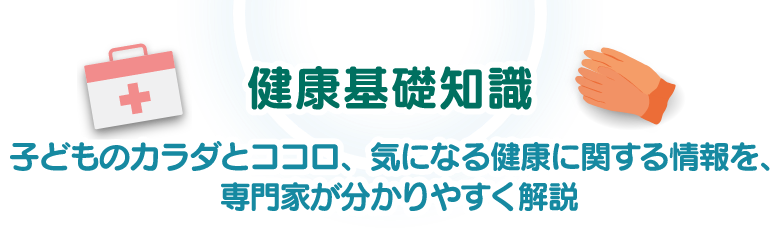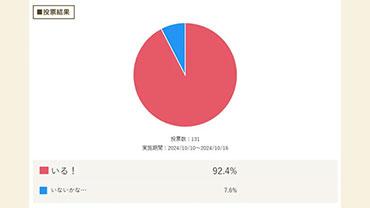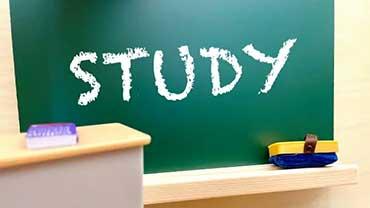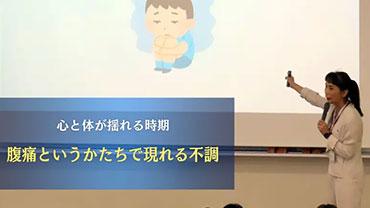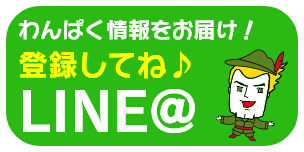2025年9月17日(水)
【素朴な疑問シリーズ】子どもの友達関係とストレスケア

夏休みが終わり、新学期が始まりました。高学年になると、友達関係で悩むことも増えてきます。小さないざこざから、場合によっては深刻ないじめまで、子どもが抱える問題はさまざまです。親としてできることは何か、どんなサポートが安心につながるのか、一緒に考えてみましょう。

高学年のいじめや友達関係の実情

文部科学省の調査によると、2023年度のいじめ認知件数は732,568件で、前年より7.4%増えています。特に高学年になると、複雑な友達関係やSNSでのやり取りが原因でトラブルが深刻化しやすくなります。
高学年では、友達との距離感やグループ内での立ち位置など、微妙な人間関係で悩むことが多くなります。表面的には落ち着いて見えても、水面下では小さな傷つきが積み重なっている場合もあります。親が「このくらい大丈夫だろう」と決めつけず、子どもの様子を丁寧に見守ることが大切です。家庭でのちょっとした会話や、今日の出来事を聞く時間が、子どもに安心感を与えるきっかけになります。

気づきのサインを見逃さない

子どもは悩みをすぐに言葉にできるわけではありません。顔色が暗い、口数が減る、急に学校へ行きたがらない…。そんな変化は心のSOSかもしれません。
例えば「なんとなくお腹が痛い」と訴えるときも、身体の不調ではなく心理的なストレスが背景にあることがあります。厚生労働省も、子どものこころの健康に関して「気持ちの変化は体の症状に表れることがある」と注意を呼びかけています。
こうしたサインに気づいたとき、親ができるのは「すぐに解決しよう」とするのではなく、「話してくれてありがとう」と受け止めること。子どもに安心感を与えることで、少しずつ本音を話せる土台ができていきます。

親ができるサポートのコツ

親ができることは、まず子どもの話をしっかり聞くことです。学校での出来事や友達関係の変化を、否定せず受け止めるだけでも子どもの安心につながります。学校との連携も重要です。学校はいじめや重大事態への対応方針を整えており、担任やスクールカウンセラーと相談することで、家庭と学校で情報を共有できます。家庭だけで抱え込まず、学校と協力して対応する姿勢を見せることが、子どもにとって大きな支えになります。
さらに、公的な相談窓口も活用できます。例えば、厚生労働省の「こころの相談統一ダイヤル」や、子どもが直接相談できる「チャイルドライン」「24時間子どもSOSダイヤル」などがあります。必要に応じて専門家に頼ることもしっかり心に留めておきましょう。

子どもの気持ちに寄り添いながら支援につなぐ

家庭では、子どもと過ごす日常の中で少し意識して関わってみましょう。登校前や帰宅後、寝る前に学校での出来事や友達関係の話を聞く時間を作ることで、子どもは安心して気持ちを話せます。困ったことがあった場合には、共感しながら受け止め、無理に解決策を提示する必要はありません。親がじっくり聞くことで、子どもは自分の気持ちを整理しやすくなります。
例えば、子どもが友達関係で悩んでいる場合には、「それは大変だったね」「そう感じるのも当然だよ」と気持ちを受け止め、学校や相談窓口を利用する方法を一緒に考えることもできます。また、親自身も「自分がしっかりしなければ」と抱え込みすぎないようにしましょう。子どもの気持ちに寄り添うことは大切ですが、親の心がすり減ってしまっては本末転倒です。「不安なときは誰かに相談していい」と子どもに伝えることは、同時に親にとっても必要な姿勢です。家庭だけで完結させるのではなく、周囲とつながることが、子どもと親の安心につながっていきます。

出展
・文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等 生徒指導上の諸課題に関する調査」
・文部科学省「令和7年3月6日新年度における法等に基づくいじめに対する平時からの備えについて」
・厚生労働省「こころもメンテしよう」
・厚生労働省「困ったときの連絡先」