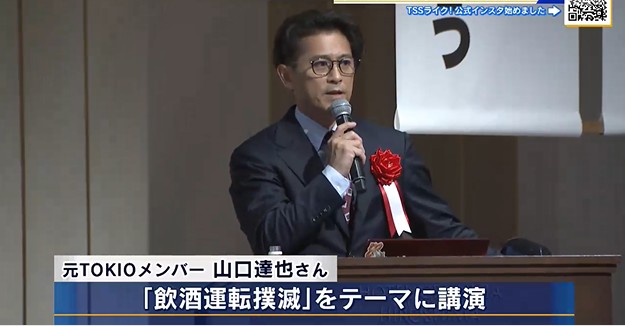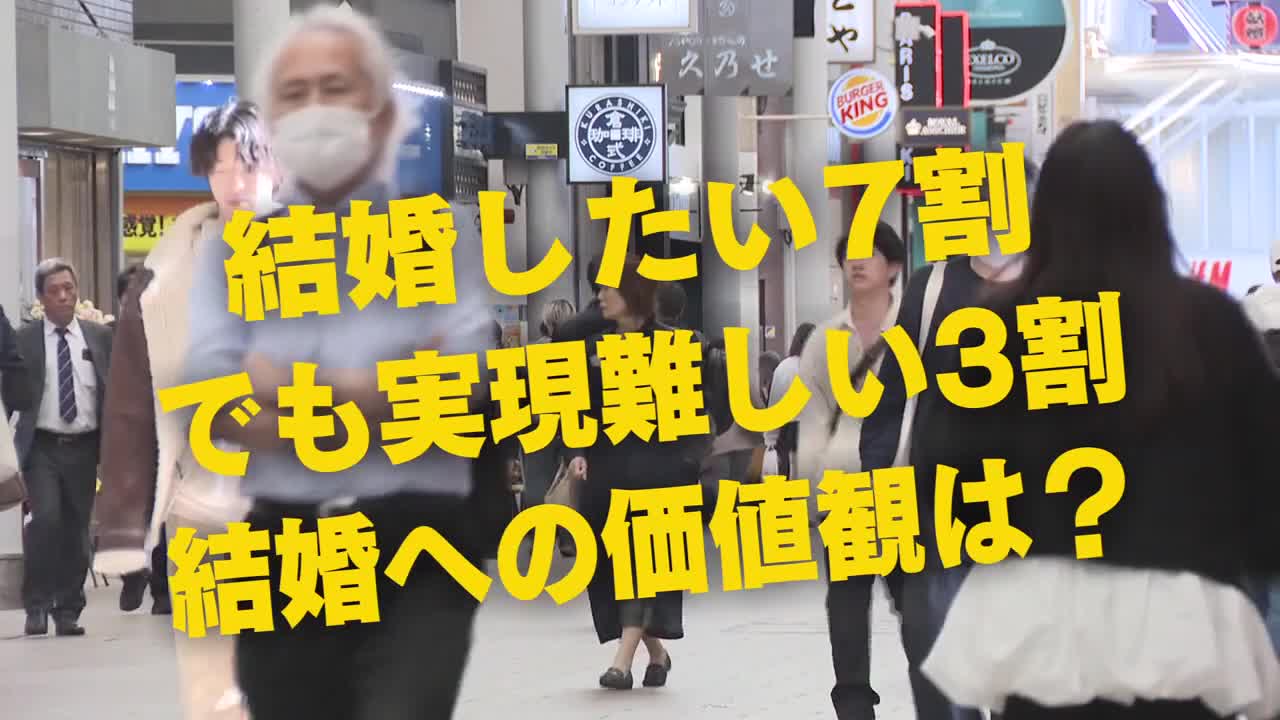“変わる広島刑務所” 新しい刑罰「拘禁刑」導入で 対話重視 受刑者の特性に合わせた更生プログラムへ
11/17(月) 19:00
明治時代から変わることのなかった刑法が今年118年ぶりに変わり、新たな刑罰が生まれました。
これまであった懲役刑と禁錮刑が一本化された、“拘禁刑”です。
その大きな特徴は、「刑務作業が義務ではない」「受刑者の年齢や障がい、依存性などを考慮して、それぞれの特性に合わせた“更生プログラム”が作られる」この2点です。
“懲らしめ”から“立ち直り”を重視した“拘禁刑”の誕生で、広島刑務所は、いま変革の時を迎えています。
その「塀」の内側に迫ります。
これまであった懲役刑と禁錮刑が一本化された、“拘禁刑”です。
その大きな特徴は、「刑務作業が義務ではない」「受刑者の年齢や障がい、依存性などを考慮して、それぞれの特性に合わせた“更生プログラム”が作られる」この2点です。
“懲らしめ”から“立ち直り”を重視した“拘禁刑”の誕生で、広島刑務所は、いま変革の時を迎えています。
その「塀」の内側に迫ります。

受刑者が刑務作業をする工場。
広島刑務所では、カープとのコラボグッズの製作が行われています。
広島刑務所では、カープとのコラボグッズの製作が行われています。

「〇〇さん要件」
受刑者を「さん」付けで呼ぶ刑務官。
以前は呼び捨てでしたが、変わったのは去年のことです。
受刑者の立ち直りを進めていくには、刑務官と受刑者の関係を構築していくことが必要不可欠だとして、昨年度、法務省は全国の刑務所に対し、受刑者を「さん」付けで呼ぶよう指示しました。
【広島刑務所 古谷大志 首席矯正処遇官】
「ある意味、刑務官としては、これまで受刑者に対して見せていた顔と別の顔を見せる場面が出てくると思いますので、1人の人間として受刑者とより向き合うことになるのかなと思います」
受刑者を「さん」付けで呼ぶ刑務官。
以前は呼び捨てでしたが、変わったのは去年のことです。
受刑者の立ち直りを進めていくには、刑務官と受刑者の関係を構築していくことが必要不可欠だとして、昨年度、法務省は全国の刑務所に対し、受刑者を「さん」付けで呼ぶよう指示しました。
【広島刑務所 古谷大志 首席矯正処遇官】
「ある意味、刑務官としては、これまで受刑者に対して見せていた顔と別の顔を見せる場面が出てくると思いますので、1人の人間として受刑者とより向き合うことになるのかなと思います」

明治時代に出来た刑法が118年ぶりに改正され、今年6月に導入された新しい刑罰が「拘禁刑」です。これまで、懲役刑の受刑者に課せられていた刑務作業が義務ではなくなり、年齢や障がいの有無など、受刑者の特性に合わせて、個別の“更生プログラム”がつくられます。
懲らしめの意味合いが強かった刑務作業は、さまざまある立ち直りの手段のうちの一つという位置づけとなりました。
拘禁刑を機に、広島刑務所では、新たな取り組みが始まっています。
懲らしめの意味合いが強かった刑務作業は、さまざまある立ち直りの手段のうちの一つという位置づけとなりました。
拘禁刑を機に、広島刑務所では、新たな取り組みが始まっています。

【竹内記者】
「刑務所内にありますこちらのビニールハウスの農場、去年新しく作られたそうです。中では広島菜が栽培されています。そして、次の収穫に向けて受刑者が土づくりを今、行っています」
農作業をしているのは、心身に障がいがあり、出所後に福祉的な支援が必要とされる受刑者です。
工場での刑務作業が困難で、これまで、個室で簡単な作業をしていたといいます。
【農業指導者】
「ゆっくりね。自分のペースでいいから」
この農場は、彼らに社会復帰に必要なスキルを身に付けてもらおうと、拘禁刑の導入に伴う取り組みの一環でつくられました。
農業の指導者のほか、福祉の専門家や多くの刑務官が立ち合い、作業を見守ります。
【窃盗の再犯受刑者(50代)】
「農場に出だして工場の担当さんに『明るくなったな』とか『元気が出てきたな』とかそういうふうなことを言われるようになりました。いま、物価高で野菜が高いじゃないですか(出所後は)自分で農作業をして、生活を少しでも楽にしたいと思っています」
重要だと考えているのは社会復帰を見据えた受刑者が、作業の大切さを理解して取り組む、“動機付け”そこが上手くいくと立ち直りの道が開ける…。
刑務所はそう考えています。
「刑務所内にありますこちらのビニールハウスの農場、去年新しく作られたそうです。中では広島菜が栽培されています。そして、次の収穫に向けて受刑者が土づくりを今、行っています」
農作業をしているのは、心身に障がいがあり、出所後に福祉的な支援が必要とされる受刑者です。
工場での刑務作業が困難で、これまで、個室で簡単な作業をしていたといいます。
【農業指導者】
「ゆっくりね。自分のペースでいいから」
この農場は、彼らに社会復帰に必要なスキルを身に付けてもらおうと、拘禁刑の導入に伴う取り組みの一環でつくられました。
農業の指導者のほか、福祉の専門家や多くの刑務官が立ち合い、作業を見守ります。
【窃盗の再犯受刑者(50代)】
「農場に出だして工場の担当さんに『明るくなったな』とか『元気が出てきたな』とかそういうふうなことを言われるようになりました。いま、物価高で野菜が高いじゃないですか(出所後は)自分で農作業をして、生活を少しでも楽にしたいと思っています」
重要だと考えているのは社会復帰を見据えた受刑者が、作業の大切さを理解して取り組む、“動機付け”そこが上手くいくと立ち直りの道が開ける…。
刑務所はそう考えています。

【広島刑務所 古谷大志 首席矯正処遇官】
「拘禁刑下においては受刑者個々の特性に応じた処遇を展開していくということですので設備面での投資をやっております」
広島刑務所の受刑者は692人。
そのうち実に85パーセントが、窃盗や薬物使用などの再犯者です。
“再犯をさせないための立ち直り支援”が課題となる中、広島刑務所が特に重視するのが“対話”です。それを象徴する部屋…。
【竹内記者】
「拘禁刑施行を機に新しくできた施設、こちらリフレクティングルーム、受刑者と刑務官が対話をする施設ということですが、中に入ってみますと緑色を基調とした暖かい明るい雰囲気です。
間接照明や観葉植物があって中央には椅子が3脚用意されています」
刑務所の中にある部屋とは思えない、明るく、おしゃれな室内。
拘禁刑の導入に合わせて、受刑者の居室を改装し、新たに用意した、“リフレクティングルーム”刑務官と受刑者が対話を行う部屋です。
「拘禁刑下においては受刑者個々の特性に応じた処遇を展開していくということですので設備面での投資をやっております」
広島刑務所の受刑者は692人。
そのうち実に85パーセントが、窃盗や薬物使用などの再犯者です。
“再犯をさせないための立ち直り支援”が課題となる中、広島刑務所が特に重視するのが“対話”です。それを象徴する部屋…。
【竹内記者】
「拘禁刑施行を機に新しくできた施設、こちらリフレクティングルーム、受刑者と刑務官が対話をする施設ということですが、中に入ってみますと緑色を基調とした暖かい明るい雰囲気です。
間接照明や観葉植物があって中央には椅子が3脚用意されています」
刑務所の中にある部屋とは思えない、明るく、おしゃれな室内。
拘禁刑の導入に合わせて、受刑者の居室を改装し、新たに用意した、“リフレクティングルーム”刑務官と受刑者が対話を行う部屋です。

一体、どのような対話が行われるのか。
記者が、受刑者側として体験しました。
【濱部刑務官】
「楽に腰かけて、クッションを前に置かれても、全然足も上げることができます」
【竹内記者】
「なるほどリクライニングなんですね。こんな感じ聞いても?」
【濱部刑務官】
「全然、大丈夫です」
受刑者1人に対し刑務官は2人。
受刑者にリラックスして話をしてもらうため、刑務官は、柔らかい物腰と口調で対話に臨みます。
ほかにも、受刑者に威圧感を与えないための工夫が。
【濱部刑務官】
「制服を着ていると強い立場と弱い立場じゃないですけど、こういうのを着てフラット(な立場で)というか」
そして、肝心な、話す内容は…
【濱部刑務官】
「気になっていることとか、話したいことがあれば、話してもらっていいので」
話題を決めるのは受刑者側。
趣味や悩み事など、何を話すかは自由です。
【濱部刑務官】
「”話し手発信“ 話し手が話したいことをしゃべる、罪の話『私は人を殺したんですけど』という話も無きにしもあらず」
【竹内記者】
「罪のことを話す方もいらっしゃれば別のことを話すことも?」
【濱部刑務官】
「そうですね。今までの経験では、『社会に出て親孝行したい。そうするために、どうしたらいいですか』とか」
受刑者と話すのは片方の刑務官のみ。
もう一人は、“観察者”として2人の対話に耳を傾けます。
対話の後、受刑者がどのような人と感じたか、話し手の刑務官と共有します。
受刑者は、その様子を第三者として見て、ほかの人から自分がどう映っているのか、客観視します。
記者が、受刑者側として体験しました。
【濱部刑務官】
「楽に腰かけて、クッションを前に置かれても、全然足も上げることができます」
【竹内記者】
「なるほどリクライニングなんですね。こんな感じ聞いても?」
【濱部刑務官】
「全然、大丈夫です」
受刑者1人に対し刑務官は2人。
受刑者にリラックスして話をしてもらうため、刑務官は、柔らかい物腰と口調で対話に臨みます。
ほかにも、受刑者に威圧感を与えないための工夫が。
【濱部刑務官】
「制服を着ていると強い立場と弱い立場じゃないですけど、こういうのを着てフラット(な立場で)というか」
そして、肝心な、話す内容は…
【濱部刑務官】
「気になっていることとか、話したいことがあれば、話してもらっていいので」
話題を決めるのは受刑者側。
趣味や悩み事など、何を話すかは自由です。
【濱部刑務官】
「”話し手発信“ 話し手が話したいことをしゃべる、罪の話『私は人を殺したんですけど』という話も無きにしもあらず」
【竹内記者】
「罪のことを話す方もいらっしゃれば別のことを話すことも?」
【濱部刑務官】
「そうですね。今までの経験では、『社会に出て親孝行したい。そうするために、どうしたらいいですか』とか」
受刑者と話すのは片方の刑務官のみ。
もう一人は、“観察者”として2人の対話に耳を傾けます。
対話の後、受刑者がどのような人と感じたか、話し手の刑務官と共有します。
受刑者は、その様子を第三者として見て、ほかの人から自分がどう映っているのか、客観視します。
【竹内記者】
「私が話した内容についてほかの人話すのを見ることがなかなかあることではないので、恥ずかしいですが、悪い思いはしない」
刑務官との対話と自分自身の見つめなおし。
この2点で、更生のきっかけをつかんでもらおうというのが狙いです。
ただ、この対話手法は、刑務官に、これまでの価値観を180度転換することを求められます。
【井上刑務官】
「自分たちの若い時も受刑者とは会話をするなと、そういうのは刑務官としては、“御法度”だった時代で育っていますから、なかなか入りは難しかったですけど、それでも終わった時の受刑者の顔見たら、和やかな顔になると、こういう一面が見られるというのは、拘禁刑になって、こういう取り組みをして、新たに変わったところだなと」
受刑者を立ち直らせるために、なにをするべきなのか…。
拘禁刑の導入によって選択肢が増えた一方、受刑者との接し方は大きな転換を求められます。
刑務官の負担が大きくなっている現実もあります。
それでも、再犯で刑務所に戻ってくる人を減らすため、刑務官たちの試行錯誤が続きます。
「私が話した内容についてほかの人話すのを見ることがなかなかあることではないので、恥ずかしいですが、悪い思いはしない」
刑務官との対話と自分自身の見つめなおし。
この2点で、更生のきっかけをつかんでもらおうというのが狙いです。
ただ、この対話手法は、刑務官に、これまでの価値観を180度転換することを求められます。
【井上刑務官】
「自分たちの若い時も受刑者とは会話をするなと、そういうのは刑務官としては、“御法度”だった時代で育っていますから、なかなか入りは難しかったですけど、それでも終わった時の受刑者の顔見たら、和やかな顔になると、こういう一面が見られるというのは、拘禁刑になって、こういう取り組みをして、新たに変わったところだなと」
受刑者を立ち直らせるために、なにをするべきなのか…。
拘禁刑の導入によって選択肢が増えた一方、受刑者との接し方は大きな転換を求められます。
刑務官の負担が大きくなっている現実もあります。
それでも、再犯で刑務所に戻ってくる人を減らすため、刑務官たちの試行錯誤が続きます。

<スタジオ>
取材した竹内記者です。随分とリラックスして対話していましたが、体験してどうでしたか?
【竹内記者】
最初は何を話そうか戸惑ったんですが、刑務官の2人が話しやすい雰囲気をつくってくれて徐々に対話が弾みました。広島刑務所は、服役中にコミュニケーション能力が培われずに出所後に社会になじめない事が多いということで、目的は「再犯の防止」なんです。そこで拘禁刑を機に、このような対話の機会を増やしたわけです。
2人とも刑務官歴30年を超えるベテランで、これまでの価値観とのギャップに難しさを感じながらも、新たな受刑者との向き合い方を模索しています。
【コメンテーター:JICA中国・新川美佐絵さん】
現場の方の負担というのは、なるべく小さくしてほしいなと思いつつ、これまでの刑罰の懲らしめでは、効果がなかったから、もしかしたら、再犯が起こってしまうということを考えると、こういった大きな転換には、やっぱり期待していきたいなと思いました。
【竹内記者】
どのような変化が起こるかというのは、これから見ていく必要があります。拘禁刑の取り組みは、まだ始まったばかりで、これから運用に向けて、試行錯誤が続けられていきます。
取材した竹内記者です。随分とリラックスして対話していましたが、体験してどうでしたか?
【竹内記者】
最初は何を話そうか戸惑ったんですが、刑務官の2人が話しやすい雰囲気をつくってくれて徐々に対話が弾みました。広島刑務所は、服役中にコミュニケーション能力が培われずに出所後に社会になじめない事が多いということで、目的は「再犯の防止」なんです。そこで拘禁刑を機に、このような対話の機会を増やしたわけです。
2人とも刑務官歴30年を超えるベテランで、これまでの価値観とのギャップに難しさを感じながらも、新たな受刑者との向き合い方を模索しています。
【コメンテーター:JICA中国・新川美佐絵さん】
現場の方の負担というのは、なるべく小さくしてほしいなと思いつつ、これまでの刑罰の懲らしめでは、効果がなかったから、もしかしたら、再犯が起こってしまうということを考えると、こういった大きな転換には、やっぱり期待していきたいなと思いました。
【竹内記者】
どのような変化が起こるかというのは、これから見ていく必要があります。拘禁刑の取り組みは、まだ始まったばかりで、これから運用に向けて、試行錯誤が続けられていきます。