船の安全を守る「海の標識」 瀬戸内海には300基以上が浮かぶ 海上保安部の整備基地にカメラが潜入
9/9(火) 18:29
全国で最も船の事故が多い瀬戸内海などを含む第六管区内で船の安全を守る海の標識…。
その整備基地を取材しました。
その整備基地を取材しました。

坂町に設置されている海上保安庁の基地…
【辰已キャスター】
「見てください!巨大なブイが何十基も並んでいますが、色も赤・緑・黄色…大きさも様々。たくさんの種類が並んでいます」
テレビカメラが入ることはほとんどなく、一般にはあまり知られていないこの基地…。
およそ70基並べられているこのブイの役割は…
【第六管区海上保安部 交通部整備課・森 関良主任技術官】
「航路になっている海で緑色が奇数の番号、赤色が偶数の番号を振っていて、来島の2番、来島の4番、来島の5番とか…」
陸上のようにつながった道路や住所がない海の上…
港の入り口などでは船の行き来が多いため、安全に航行できるよう灯台などの航路標識が設置されています。
【辰已キャスター】
「見てください!巨大なブイが何十基も並んでいますが、色も赤・緑・黄色…大きさも様々。たくさんの種類が並んでいます」
テレビカメラが入ることはほとんどなく、一般にはあまり知られていないこの基地…。
およそ70基並べられているこのブイの役割は…
【第六管区海上保安部 交通部整備課・森 関良主任技術官】
「航路になっている海で緑色が奇数の番号、赤色が偶数の番号を振っていて、来島の2番、来島の4番、来島の5番とか…」
陸上のようにつながった道路や住所がない海の上…
港の入り口などでは船の行き来が多いため、安全に航行できるよう灯台などの航路標識が設置されています。

その標識のひとつが海に浮かぶ「灯浮標」。
おもに障害物の目印になったり航路を示したりするなどの役割を担っていて、瀬戸内海など第六管区内には“全国最多”の302基が設置されています。
そのほとんどを管理・整備しているのが坂町にあるこの基地です。
【第六管区海上保安部 交通部整備課・森 関良主任技術官】
「(海につかる部分は)ここから下は貝殻が付きにくい塗料を塗っている。隣を見ると赤茶色のような…貝殻がつくとブイが沈んでいくことがあるので」
【辰已キャスター】
「本当に大きいですね」
【森さん】
「これでもこの中で小さいほう…」
おもに障害物の目印になったり航路を示したりするなどの役割を担っていて、瀬戸内海など第六管区内には“全国最多”の302基が設置されています。
そのほとんどを管理・整備しているのが坂町にあるこの基地です。
【第六管区海上保安部 交通部整備課・森 関良主任技術官】
「(海につかる部分は)ここから下は貝殻が付きにくい塗料を塗っている。隣を見ると赤茶色のような…貝殻がつくとブイが沈んでいくことがあるので」
【辰已キャスター】
「本当に大きいですね」
【森さん】
「これでもこの中で小さいほう…」

そして、これが“最も大きい”灯浮標…。
【第六管区海上保安部 交通部整備課・森 関良主任技術官】
「この部分までがだいたい海に浸かっている状態…」
【辰已キャスター】
「ちょっとした建物ですね」
基地では数年に1度、損傷した部品の修理や塗装・交換を行うほか、重りと繋ぐチェーンの確認など年間40から60基のメンテナンスをしているといいます。
今回特別に、灯浮標の内部も見せてもらいました。
【辰已キャスター】
「あ!広ーい!」
【森さん】
「直径が2.6mある。円形のものが電池を入れるものになっていて」
おもにソーラーパネルで充電するための機器が入っていて、標準で6個の電池が装着されていますが、光の明るさや大きさによって電池の数は異なるといいます。
【第六管区海上保安部 交通部整備課・森 関良主任技術官】
「この部分までがだいたい海に浸かっている状態…」
【辰已キャスター】
「ちょっとした建物ですね」
基地では数年に1度、損傷した部品の修理や塗装・交換を行うほか、重りと繋ぐチェーンの確認など年間40から60基のメンテナンスをしているといいます。
今回特別に、灯浮標の内部も見せてもらいました。
【辰已キャスター】
「あ!広ーい!」
【森さん】
「直径が2.6mある。円形のものが電池を入れるものになっていて」
おもにソーラーパネルで充電するための機器が入っていて、標準で6個の電池が装着されていますが、光の明るさや大きさによって電池の数は異なるといいます。
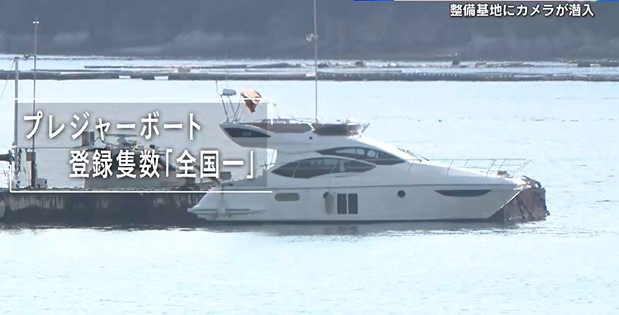
プレジャーボートの登録隻数が全国で一番多い広島。
コンテナや車の輸出など貿易船の行き来もあることから、全国で最も事故が多い第六管区内で身近な海の安全を守る海の標識…
一方、灯浮標の存在は船に乗らない人でも知っておくべき理由がありました。
《スタジオ》
海での交通ルールの目印になっている灯浮標。
匹田さん、灯浮標の存在は知っていました?
【コメンテーター:広島大学大学院・匹田篤准教授】
「恥ずかしながら全然知らなかったですね。灯浮標という名前も初めて聞きました」
私も聞き馴染みがないものでしたが、知っておいて損はないというか、いざというとき助けてくれる存在になるかもしれません。
例えば、釣りの最中や遊泳中に流されてしまったという場合、まず灯浮標が近くにあったら、118番通報をしてください。
そして、それぞれの灯浮標に付いている名前と番号を伝えてください。
海の上にいても自分の座標、どこにいるかというのがわかります。
いざというとき助けになってくれます。
コンテナや車の輸出など貿易船の行き来もあることから、全国で最も事故が多い第六管区内で身近な海の安全を守る海の標識…
一方、灯浮標の存在は船に乗らない人でも知っておくべき理由がありました。
《スタジオ》
海での交通ルールの目印になっている灯浮標。
匹田さん、灯浮標の存在は知っていました?
【コメンテーター:広島大学大学院・匹田篤准教授】
「恥ずかしながら全然知らなかったですね。灯浮標という名前も初めて聞きました」
私も聞き馴染みがないものでしたが、知っておいて損はないというか、いざというとき助けてくれる存在になるかもしれません。
例えば、釣りの最中や遊泳中に流されてしまったという場合、まず灯浮標が近くにあったら、118番通報をしてください。
そして、それぞれの灯浮標に付いている名前と番号を伝えてください。
海の上にいても自分の座標、どこにいるかというのがわかります。
いざというとき助けになってくれます。









