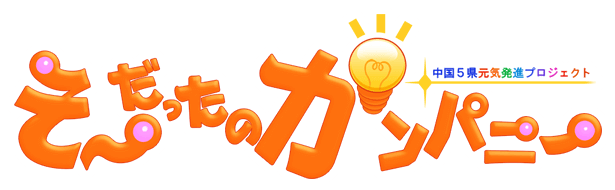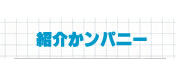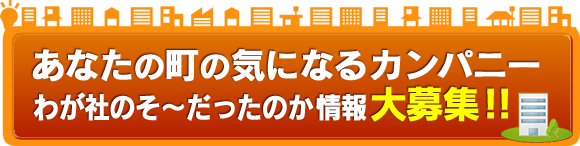株式会社 サタケ(広島県)
酒づくりの未来を変えた挑戦
今回は、日本酒の常識を覆す精米技術を開発した、広島県のカンパニー「サタケ」が登場!明治時代、日本初の動力式精米機を生み出し、吟醸酒の誕生を支えたサタケ。しかし現代では、日本酒離れや精米技術の限界に直面し、社内からは事業撤退の声も…。そんな中、創業の原点を守るため、自ら“精米の未来”を切り拓く決断を下します。そして試行錯誤の末に誕生したのが、新しい精米機「真吟」。雑味を抑え、旨みを引き出すその技術は、今や多くの酒蔵から高評価を得るまでに。今回は、日本酒に革新をもたらしたカンパニーのそ~だったのか!に迫ります。


老舗精米機メーカーに迫られた決断
酒づくりの町・西条にある精米機メーカー「サタケ」。1896年、日本初の動力式精米機を開発。1908年には、砥石で米を削る精米機を開発し、より早く・多くの米を削れるようになり、この技術が吟醸酒の誕生を支えました。日本酒の進化を支えてきたカンパニーは国内大型精米工場で使われる精米機の7割を手がけるトップメーカーへと成長。しかし、2000年代、酒造用精米機の需要が減少していきます。それは、カンパニーの精米機が頑丈で、一度購入すると、次の購入につながらなかったことと、食の多様化により、日本酒の消費が年々減少したこと。そんな中、社員から「酒造用精米機の事業から撤退」という提案まで出たのです。しかし、カンパニーは創業の原点を守るため、2015年、新たな酒造用精米機の開発に踏み切ったのです。


精米機の要・砥石を変え、新たな精米機が誕生
酒造用精米機は、米を回転する砥石に何度も通し、少しずつ丁寧に削っていきます。カンパニーが目指したのは、これまでの精米を進化させること。割れないように、早く・美しく米を削るという性能を実現するため、容器の形状や砥石の回転速度など、条件を少しずつ変えながら、試行錯誤していました。しかし、品質は良くなったものの、精米時間は変わらないまま。足踏み状態から2年、ある技術者から、これまでのものより硬い工業用の砥石に変えてみてはと提案されたのです。砥石は明治時代から改良を重ねてきた精米機の要。しかし、わずかな可能性に賭けて試した結果、削るスピードは期待したほど上がりませんでしたが、米はこれまでの丸い形ではなく、理想とされる“扁平な形”になっていたのです。4年の歳月をかけて精米機を完成させたカンパニーは、この新しい精米技術に「真吟」という名前を付けました。