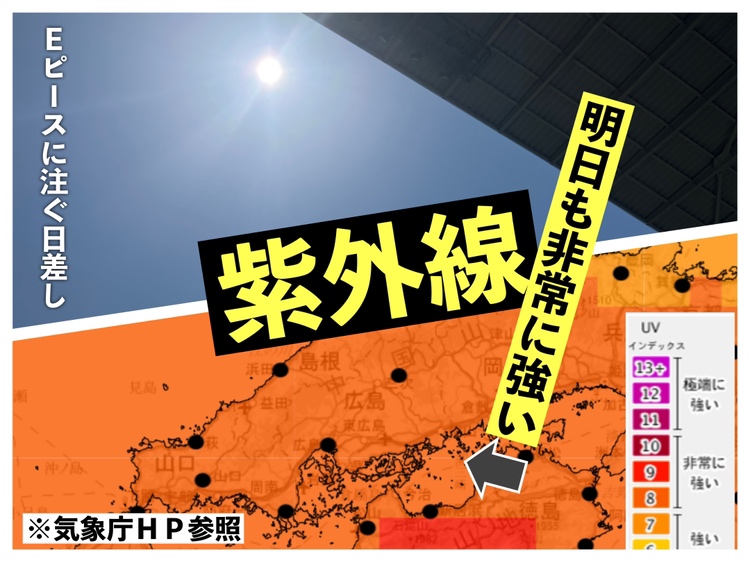ドライバーのごみポイ捨て問題 トラックのETC無料化などがドライバーの待遇改善のカギに
12/20(水) 18:48
「TSSライク!」では、シリーズ企画として、「トラックドライバーのポイ捨て問題」について考えています。3日目の今回は、残業時間の上限が定められるいわゆる2024年問題が来年に迫る中、この問題を考えていきます。
トラックドライバーが路上駐車する場所。その近くには、たくさんのごみが捨てられている…。そんなポイントが広島県内にいくつかあります。
そこには、荷物の積み降ろしの順番を長時間待たなければならない、「荷待ち」と言われるトラックドライバー特有の労働環境も要因の一つです。
一方、高速道路のサービスエリアにもごみのポイ捨てが多くみられました。
人気のユーチューバーでもあるベテラントラックドライバーに聞くと…。
【トラックユーチューバー・おじとらさん】
「高速道路の乗るところ、降りるところ、そこの見えないところで、後ろから付いていると、前の車が窓から投げ捨てたりとかそういった光景は少なからず見ることがあります」
ごみの収集作業を取材すると・・・
【ネクスコ西日本小谷サービスエリア・クリーンスタッフ】
「こういうボトルもすごく多いです」
それは、排せつ物が入ったペットボトルでした。
広島県トラック協会も把握していて、ポスターで注意喚起をしています。
【広島県トラック協会・森井茂人 専務理事】
「雑誌であったり、飲み物の空き缶であったり弁当がらであったり、そして排せつ物であったりというものが捨てられているというのが現状だという風に思っております。ドライバーの意識を変えていくということも必要なんですけれども、ポイ捨てしないような社会環境に、社会と一体となってやっていく必要があるのではないのか」
そう話す背景には、トラックドライバーの労働環境があります。専門家は。
【広島大学大学院 社会科学研究科・角谷快彦 教授】
「トラックドライバーの労働環境というのは、規制緩和の進行によって厳しさを増して、1990年に、認可運賃だったのが、運賃が届け出制になったことでより自由な価格競争が生まれるようになった。あと、免許制が認可制になって新規参入がしやすくなった。競争が激しくなって、価格が低下して賃金が下がっていった」
1990年に全国およそ4万社だった事業者は30年間で26万社まで増えたのです。
【広島大学大学院 社会科学研究科・角谷 快彦 教授】
「トラック事業者の経営環境も悪化して、高速道路では、ETCの深夜料金は大体3割引きになるが、深夜にトラック渋滞が起きる。コスト削減のため。いわゆる深夜集中というのが起きて、それまではレストランとか食堂とかで食事をしていたのが、コンビニで買って車内食という形になって、それに伴ってポイ捨てが増えていくような構図だと思う」
これが、排せつ物の入ったペットボトルのポイ捨ての要因の一つに挙げられています。
一方で、
【トラックユーチューバー・おじとらさん】
「そういうときのために、簡易的な…お見せするとこういった携帯トイレ。こういうものをトラックに今、たくさん積んでいるんですよ。使う頻度はまずないですけれどあるに越したことはないので」
対策をしているドライバーもいるのです。
トラック業界は、来年2024年に、残業規制が始まり、これまでの無制限から年間残業時間の上限が960時間になります。
専門家は、この影響がポイ捨てにも出てくると予想します。
【広島大学大学院 社会科学研究科・角谷 快彦 教授】
「悪化すると思いますね。より限られた労働時間で多くの荷物を運ばないといけない。
車中食というのがまた増えていって、ポイ捨てにつながるということは十分に考えられます。また、労働環境が悪くなるということなので、残業代で今まで頼りに生活をしていた方が離職されたりするので、より少ないドライバーの数で、増え続ける荷物に対処しなきゃいけない。休憩時間というのは削られていく可能性が高くてそうなると労働環境が悪くなると思います」
そうならないために、どうすればいいのでしょうか。
【広島大学 大学院 社会科学研究科・角谷 快彦 教授】
「1にも2にも、政府が労働生産性の向上のための投資をするということだと思う。例えばインフラ投資、道路がよくなればスムーズに荷物を運べるようになるし、あと補助金。例えば、トラックのETC料金を無料にして高速道路料金を払わなくていいようにするとか、そういうことで運輸業に余裕が生まれてドライバーの待遇も改善されていく可能性が高い。また将来に向けた、高速道路例えば、自動運転技術の開発とか、そういった研究開発投資も将来の労働生産性向上のために重要だと思う。労働生産性が向上すれば、おのずとドライバーの待遇もよくなる。そこらへんが鍵だと思います」
私たちの生活に欠かせない荷物を運んでくれるトラックドライバー。
その労働環境の改善に目を向けることがポイ捨てを減らす第一歩になりそうです。
トラックドライバーが路上駐車する場所。その近くには、たくさんのごみが捨てられている…。そんなポイントが広島県内にいくつかあります。
そこには、荷物の積み降ろしの順番を長時間待たなければならない、「荷待ち」と言われるトラックドライバー特有の労働環境も要因の一つです。
一方、高速道路のサービスエリアにもごみのポイ捨てが多くみられました。
人気のユーチューバーでもあるベテラントラックドライバーに聞くと…。
【トラックユーチューバー・おじとらさん】
「高速道路の乗るところ、降りるところ、そこの見えないところで、後ろから付いていると、前の車が窓から投げ捨てたりとかそういった光景は少なからず見ることがあります」
ごみの収集作業を取材すると・・・
【ネクスコ西日本小谷サービスエリア・クリーンスタッフ】
「こういうボトルもすごく多いです」
それは、排せつ物が入ったペットボトルでした。
広島県トラック協会も把握していて、ポスターで注意喚起をしています。
【広島県トラック協会・森井茂人 専務理事】
「雑誌であったり、飲み物の空き缶であったり弁当がらであったり、そして排せつ物であったりというものが捨てられているというのが現状だという風に思っております。ドライバーの意識を変えていくということも必要なんですけれども、ポイ捨てしないような社会環境に、社会と一体となってやっていく必要があるのではないのか」
そう話す背景には、トラックドライバーの労働環境があります。専門家は。
【広島大学大学院 社会科学研究科・角谷快彦 教授】
「トラックドライバーの労働環境というのは、規制緩和の進行によって厳しさを増して、1990年に、認可運賃だったのが、運賃が届け出制になったことでより自由な価格競争が生まれるようになった。あと、免許制が認可制になって新規参入がしやすくなった。競争が激しくなって、価格が低下して賃金が下がっていった」
1990年に全国およそ4万社だった事業者は30年間で26万社まで増えたのです。
【広島大学大学院 社会科学研究科・角谷 快彦 教授】
「トラック事業者の経営環境も悪化して、高速道路では、ETCの深夜料金は大体3割引きになるが、深夜にトラック渋滞が起きる。コスト削減のため。いわゆる深夜集中というのが起きて、それまではレストランとか食堂とかで食事をしていたのが、コンビニで買って車内食という形になって、それに伴ってポイ捨てが増えていくような構図だと思う」
これが、排せつ物の入ったペットボトルのポイ捨ての要因の一つに挙げられています。
一方で、
【トラックユーチューバー・おじとらさん】
「そういうときのために、簡易的な…お見せするとこういった携帯トイレ。こういうものをトラックに今、たくさん積んでいるんですよ。使う頻度はまずないですけれどあるに越したことはないので」
対策をしているドライバーもいるのです。
トラック業界は、来年2024年に、残業規制が始まり、これまでの無制限から年間残業時間の上限が960時間になります。
専門家は、この影響がポイ捨てにも出てくると予想します。
【広島大学大学院 社会科学研究科・角谷 快彦 教授】
「悪化すると思いますね。より限られた労働時間で多くの荷物を運ばないといけない。
車中食というのがまた増えていって、ポイ捨てにつながるということは十分に考えられます。また、労働環境が悪くなるということなので、残業代で今まで頼りに生活をしていた方が離職されたりするので、より少ないドライバーの数で、増え続ける荷物に対処しなきゃいけない。休憩時間というのは削られていく可能性が高くてそうなると労働環境が悪くなると思います」
そうならないために、どうすればいいのでしょうか。
【広島大学 大学院 社会科学研究科・角谷 快彦 教授】
「1にも2にも、政府が労働生産性の向上のための投資をするということだと思う。例えばインフラ投資、道路がよくなればスムーズに荷物を運べるようになるし、あと補助金。例えば、トラックのETC料金を無料にして高速道路料金を払わなくていいようにするとか、そういうことで運輸業に余裕が生まれてドライバーの待遇も改善されていく可能性が高い。また将来に向けた、高速道路例えば、自動運転技術の開発とか、そういった研究開発投資も将来の労働生産性向上のために重要だと思う。労働生産性が向上すれば、おのずとドライバーの待遇もよくなる。そこらへんが鍵だと思います」
私たちの生活に欠かせない荷物を運んでくれるトラックドライバー。
その労働環境の改善に目を向けることがポイ捨てを減らす第一歩になりそうです。